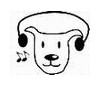 |
fmラジオ局#受信のつぼ |
FMアンテナの作り方 |
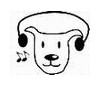 |
fmラジオ局#受信のつぼ |
FMアンテナの作り方 |
1.fm放送が受信できない!? 2.アンテナ、ブースターの効果 3.fmラジオ局チャンネル fm福岡,fm802,bay fm他 4.FMアンテナスタイルブック 5.FMラジオへつなぐ 6.FMアンテナの作り方 7.FM受信ブースターAMP 8.FM受信ノイズ対策 9.FM受信ラジオ本体 10.あのFMラジオ局は? 11.デジタルラジオ 12.掲示板 13.管理人室 管理人(freeman)の連絡先は freemanあっとnakayoshi.cc (あっとは@に変更) 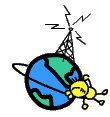 |
6.FMアンテナの作り方アンテナとしてどんな長さでもいいのは、放送局に近い場合で、マンションの中や郊外での受信では周波数にあった長さのアンテナ線が必要になります(共振)。ただし厳密に放送周波数にあわせる必要はありませんし、複数のFM放送局を聞くわけですから厳密な長さにすることもできません。このホームページでの実験での中心周波数として80MHzとしました。 なお、89cmを1/4波長、1/2波長を=178cmとします(3.FMアンテナスタイルブック参照)。 A)単線アンテナ 89cm(1/4波長)の単線を直でラジオにつなぎます。 B)ダイポールアンテナ 89cm(1/4波長)の単線を2本直でラジオにつなぐかまたは外部に出す場合はフィーダーを使う場合はフィーダー(同軸線)の端の芯線と編み線にそれぞれ89cm単線をつけてダイポール型アンテナまたは片方をカウンターポイズにみたてたバーチカルアンテナとします。この場合、編み線側の線は窓枠などにそって貼り付け、芯線側はだらりとたらしてもよし、T字型にしてもよし(T字に対して垂直方向に指向性がでますので方向の調整が必要です)。 C)ループアンテナ 1周が1波長(356cm)のループアンテナで完全な円とする必要はありません。四角や多角形でもいいです。ただし長方形にするとダイポールアンテナにちかずきアンテナゲインは多少少なくなりますが聞いて分かるほどではないです。 実験したのは四角形です。 壁にはりつけ  5mmのガラエポ丸棒で十字の支柱をつくりアンテナ線を張る。  アンテナ線とフィーダーとのつなぎ方  ベランダにループアンテナとりつけ。これが一番よかった。 D)フィーダー アンテナからラジオまでつなぐ線をフィーダーを呼びますが、同軸線やAC(平行)コードを用います。周辺ノイズが 入ってくる場合はフィーダーに飛び込んでくる場合があります。その場合は、ラジオに近いところにコモンモードチョークを入れます。管理人の場合はブースターアンプの増幅度を上げたのでノイズが大きくなりコモンモードチョークをいれるとかなりノイズがへりました。  E)結合コイル ラジオにアンテナ接続用の端子が無い場合、写真のようなコイルを用いてアンテナとラジオ内部の入力同調回路へ電波を誘導します。アンテナ(フィーダー)とコイルを圧着端子でつないでいます。同軸フィーダーの場合はコイルの線の両方ともフィーダーにつなぎます。 単線アンテナの場合、コイルの片方は開放(なにもつながない)でいいです。 F)電子工作入門 F-1)電線の工作 アンテナに使う電線は、被覆電線です。金属(銅)芯線は細い線をより合わせたものがおおく、それを使います。まとめた芯線の太さで規格の呼び名となっていて0.75スケとか1.25スケ(1.25の2乗、太さ1.25mm)とかあります。フィダー線は同軸ケーブルというタイプでホームセンターなどでは3V2Cタイプしかない場合があります。管理人は1.5D2Vという細いタイプを使いました。またアンテナ線にも使っています。フィーダーとしてACコードを使ってもいいです。 金属部分を使うのですから、ビニールの被覆を剥ぎ取る必要があります。専用の工具=ワイヤーストリッパーがあります。いろんな種類がありますが使いやすいのは写真のタイプです。  F-2)電線の結合 電線同士(電線の金属線部分)をつなぎ合わせるには、半田とハンダをとかす半田ゴテという工具が必要です。単に線同士をねじり合わせてもいいですが時間がたつとほどけて接触不良になります。  半田のほかに圧着(あっちゃく)という方法もあります。こちらも専用の圧着端子と圧着工具があります。  |
|
| このホームページの 管理人(freeman)の連絡先は freemanあっとnakayoshi.cc(あっとは@に変更) (c)2006Dec.7 by freeman: all rights reserved |